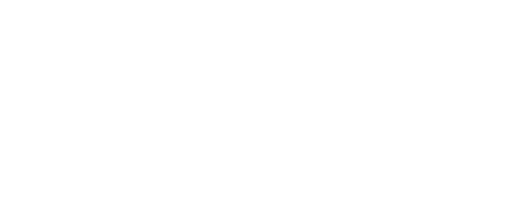医療法人明医研は、「WARM(温かく)&RELIABLE(信頼に足る)」という理念のもと、地域の人々の健康を守り、苦悩を和らげ、心ゆく日々を支えることで、現在と未来の世代に貢献していきたいと考えております。
わたしたちは、その名のとおり医師をはじめとして、外来看護師、訪問看護師、臨床検査技師、理学療法士、ヘルパー、事務など様々な職員が、明るい職場で、新しいことに挑戦し、納得する医療・ケアを提供するために、互いに研鑽しながら、時代の要請に応えていきたいという想いを共有しています。
多職種連携における質の高い医療・介護サービスの向上を目指したい方、医療・介護サービスによる地域貢献を目指している方が仲間に加わって頂けるのを心よりお待ちしております。
お知らせ
お知らせはありません。
募集職種
クリニック
非常勤医師
※現在募集しておりません
医師事務作業補助者
※現在募集しておりません
医療事務
※現在募集しておりません
訪問看護ステーション
訪問看護師
※現在募集しておりません
理学療法士(PT)
※現在募集しておりません
主任介護支援専門員
※現在募集しておりません
医療事務
※現在募集しておりません
ヘルパーステーション
法人本部
法人本部
※現在募集しておりません
ご応募
- 個人情報は個人情報保護方針に関する基本方針にもとづき、適切に取り扱います。
お電話でのご応募
法人本部 採用担当
048-875-7884(平日 月~金/9:00~18:00)
ご応募の際は「医療法人明医研の求人サイトを見た」とお伝え下さい。
フォームでのご応募
下記エントリーフォームより必要事項をご入力の上、ご応募ください。
- このフォームは【採用応募者専用】です。営業目的・各種法人様からのお問い合わせへの使用はご遠慮ください。応募者以外からの送信は、業務妨害とみなし、しかるべき対応を行う可能性があります。
お問い合わせ
- 個人情報は個人情報保護方針に関する基本方針にもとづき、適切に取り扱います。
お電話でのお問い合わせ
法人本部 採用担当
048-875-7884(平日 月~金/9:00~18:00)
フォームでのお問い合わせ
下記フォームより必要事項をご入力の上、お問い合わせください。
- このフォームは【採用応募者専用】です。営業目的・各種法人様からのお問い合わせへの使用はご遠慮ください。応募者以外からの送信は、業務妨害とみなし、しかるべき対応を行う可能性があります。